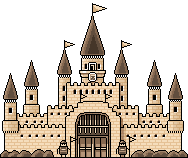<ぶらり和歌山>
【和歌山城】
和歌山城は、天正13年(1585)に紀州を平定した豊臣秀吉が弟の秀長に築城させたのが始まり。
その築城を担当したのが、築城の名人藤堂高虎。
まず、秀長の城代として桑山重晴が入り、慶長5年(1600)には、浅野幸長が入城。
そして、元和5年(1619)には徳川家康の第10男・頼宣が入城、紀州55万5千石の城となり、
以来、水戸・尾張と並び、徳川御三家のひとつとして、長い歴史を刻む。
江戸時代に和歌山城は別名「虎伏竹垣城」と呼ばれていたそうです。
これは、和歌山城の建つ山が虎の伏した姿に似ていたためと言われています。
また、その昔天守閣は和歌山弁で「おてんしゅ」→「おてんす」と呼ばれてきました。
   
※久しぶりにリフレッシュできました!
|

和歌山城 |
標高約49mの虎伏山の上に建てられ
白壁の天守閣の美しさから、
別名「白亜(はくあ)城」、
山の名前を取って「虎伏城」
 |

連立式天守 |
天守閣は、大天守と小天守、台所、
乾櫓、二門櫓などが連結したり多聞櫓
(石垣の上にある櫓)で繋がっているつくりで、
楠門を閉めるとそれらが塀で囲われて
大きな要塞になるという構造。
今日本にある連立式天守は
和歌山城・姫路城・松山城の3城だけ。 |

石垣 |
和歌山城の石垣には、
紀州特産の青石(緑泥片岩)が多く、
時代の移り変わりを表すかのように
いろんな種類の石垣が存在
 |

西の丸庭園 |
紀伊徳川家初代藩主
徳川頼宣が築造した城郭庭園屈指の名園
 |

御橋廊下 |
江戸時代には藩主とお付の者だけが
藩の政庁や藩主の生活の場である二の丸と
紅葉渓庭園のある西の丸を行き来するため
に架けられた橋。
屋根を設け、外からは見えないつくり。
斜め(約11度の角度)に架かる橋としては、
全国的にも珍しい構造 |

裏坂登り口にある「木の根っこ」 |
石の階段の下の方から覗くと、
木の根っこが階段をよじ登る
小人に見えるそうです。
 |